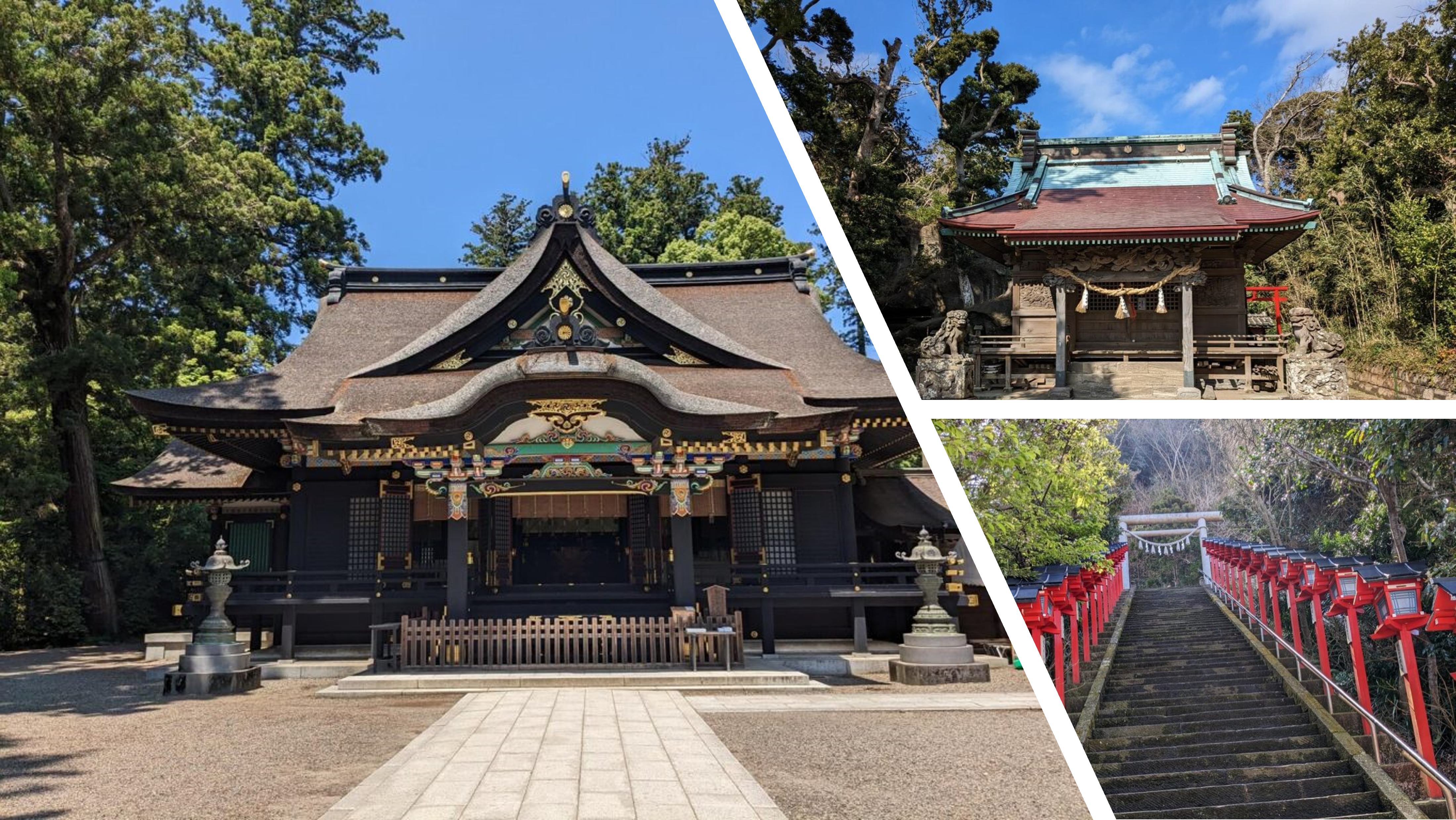「香取海を巡る神々」の本論を理解する際に、役に立つと思われる項目について、「コラム」に取り上げ、簡単にまとめておこうと思う。まずは「氏姓制度」についてである。
氏姓制度
ヤマト王権はさまざまな豪族が集まり、のちに「天皇」と呼ばれる大王を中心に形成された連合組織のようなものであったと考えられる。 中央の組織が上手く機能するように、さらに地方の豪族を含めて支配が円滑に進むように、5 ~ 6 世紀にかけてつくり上げたしくみが「氏姓制度」である。
氏とは
「氏(うじ)」とは直木孝次郎氏によれば、「朝廷に官吏として仕える有力者を中心とする血縁集団」であり、より詳しくは「有力な家を中心として、その血縁および非血縁の家によって構成される同族団またはその連合体」と定義されている。ここで「朝廷に官吏として仕える」という部分が重要で、王権に従わない地方首長のことは「氏」とは呼ばない。「『土蜘蛛』と呼んだり、『八十梟帥(やそたける)』『魁師(ひとごのかみ)』と呼んだり、また東北地方の住民を『蝦夷(えみし)』、九州南部の住民を『隼人』などと呼んでいる(水谷千秋「日本の豪族100」)。「氏」の名は、一般的に、住んでいる土地の名、祖先の名、あるいは世襲する職業名をとってつけられている。
姓とは
「姓(かばね)」とはヤマト王権が与えた「氏の政治的地位を表す称号」であり、水谷千秋「日本の豪族100」によれば、それぞれつぎのような意味を持っている。
- 臣(おみ):畿内の有力豪族。王権への従属度が高い。蘇我臣、春日臣、紀臣など。
- 連(むらじ):一定の職掌を以て王権に仕える。従属度のより強い豪族。大伴連、中臣連、物部連など。
- 君(きみ):地方・畿内の有力豪族。王権から比較的独立した性格を持つ。
- 直(あたい):畿内の中小豪族。および渡来系豪族。
- 造(みやつこ):渡来系豪族
- 首(おびと):畿内の中小豪族。
(2023/08/10)