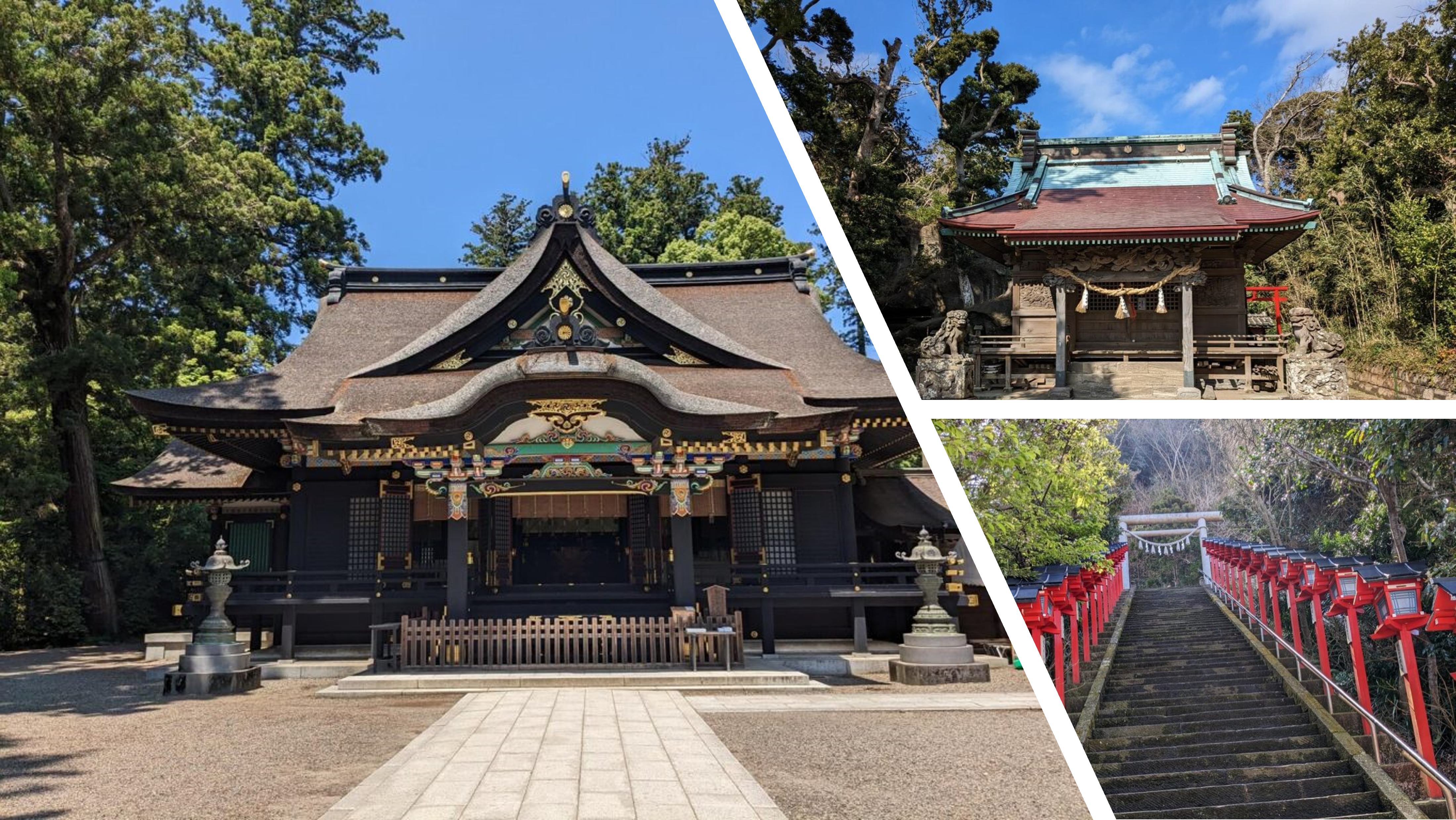ヤマト王権の地方経営制度の変遷
- 4 ~ 5 世紀、東国では各地に有力豪族が生まれ、ヤマト王権と結びつく豪族も相当数あった。それぞれが自分の勢力の及ぶ地域の「国主(クニヌシ)」だった。「大国主」はたくさんの国をたばねた存在「オオ・クニヌシ」というわけだ。
- ヤマト王権は国土の統一支配を進展させるべく、「クニ」という行政圏を設定し、その地域でもっとも有力な豪族を地方長官である「国造(くにのみやつこ)」に任命する制度を導入した。この「国造制」は遅くとも 6 世紀ごろまでには導入を完了している。この制度のもとで、「国造は、はじめ独立性が強かったが、次第に中央の統制に服し職掌も規格化する。(一)子弟が舎人・靫負、むすめや姉妹が采女として出仕すること、(二)特産物や馬・兵器などの供出、(三)物品の製作、またはその費用の負担、(四)部民や屯倉を管理する伴造の職務の兼務、(五)皇室・中央豪族などの巡行に際しての接待や献上、(六)いわゆる国造軍を率い部内の警備警察や外征に従うこと(国史大事典)」などの義務を負った。なお、(四)に出てくる「部民」「屯倉」についてはあとで説明する。
- 大化の改新(645 年)で、ヤマト王権はさらに中央集権化を推し進めるために、各地の「国造」の「クニ」を分割・再編して「調(こおり)」を置き、国ー評ー里とした。大宝律令後は「調」は「郡(こおり)」となり、国ー郡ー里となった。例えば、鹿島は[常陸国」ー「香島郡」となっている。「国」は朝廷から派遣される「国司(くにのつかさ)」(「常陸国風土記」では「総領」と呼んでいる)が統治し、「郡」は「郡司(こおりのつかさ)」が政務をとった。「国」の政庁を「国衙(こくが)」あるいは「国庁」といい、政庁所在地を「国府」といった。「郡」の役所を「郡家(ぐうけ)」(「郡衙(ぐんが)」「郡府」ともいう)と呼んだ。「郡司」には、「国造」がスライドしている例が多い。
部民制
「部民制」とは 6 世紀前半までには成立したと思われるヤマト王権の「職務分掌の制度」であるとともに、「地方支配の制度」でもある。「もともと畿内およびその周辺の中小豪族が朝廷の各種の職務を世襲的に分掌する組織を『トモ』と呼んだのが始まりであったが、のちには制度が拡充され、米や食材の貢納や、渡来人の生産する玉類や武器などの手工業品の貢献義務を負う者などにも『トモ』という言葉が使われるようになった。そして『トモ』」に漢語の「部」の字が与えられるようになった。(水谷千秋「日本の豪族100」)
篠川賢の「国造」によれば、「部」の構成については、朝廷に出仕し何らかの職務に従事した人々である「トモ」と、その「トモ」を出仕させ、それを資養する(「トモ」の生活を経済的に支える)義務を負わされた在地の集団である「ベ」との二つに分けて捉える説が一般的であり、「部」は、全国各地に設置されたのであり、各地から出仕してきた「トモ」を率いたのが中央の「伴造」であり、各地の「ベ」集団を現地で統率したのが地方の「伴造」であるとしている。
また、川尻秋生「板東の成立」によれば、部民には大きく分けてつぎの三種類がある。
- 刑部・長谷部などの名代(なしろ)・子代(こしろ):名代とは王族の功績を後世に伝えるために置かれた部、子代とは皇子のために設定した部で、具体的は天皇・皇后・皇子の宮号ないし名をつけた部のことであり、王権に服属した地方豪族の一部とその支配下にある民衆が割き取られ、その豪族は、○○部直として地域伴造として、在地の部民を管掌した。地方伴造の一部は「国造」に任じられ、彼らの子弟は舎人(宮の警備担当)、靫負(ゆげい、大王の軍事担当)、膳夫(かしわで、大王の食事担当)として王権に仕えた。そして、各地から出仕した地方伴造は、中央で中央伴造によって統括された。
- 忌部(いんべ)・玉作部(たまつくりべ)など、王権に奉仕する職業部:先に述べた中央伴造ー地方伴造ー部民という関係は職業部にも当てはまる。
- 蘇我部(そがべ)・巨勢部(このせべ)など、豪族が所有する部曲(かき)。部曲についても、中央伴造を中央豪族(蘇我・巨勢氏など)に置き代えれば、名代・子代と同様の関係となる。
5 世紀中頃から後半にかけては、「トモ」が拡大していく時期であり、当時めざましい成長を遂げていた「大伴氏」などは、「その大いなるトモ」という氏の名に彼らが台頭した時期が反映されている。一方これに続いて台頭した物部氏は、「部」を氏の名に含んでいることから、大伴氏よりやや新しい時期に台頭したと考えられる。事実、「大伴氏」も「物部氏」はいずれも列島各地に濃密に分布している(水谷千秋「日本の豪族100」)。
屯倉
また、ヤマト王権は各地に大王家の直轄領を置いた。御宅・三宅・官家、また屯倉・屯宅・屯家などと表記し、「ミヤケ」とよむ。国史大辞典によれば、「畿内周辺および近国の屯倉は水田の経営と、稲穀の貢進を目的としているが、中・遠国の屯倉はそれと異な」り、「(一)水田、(二)可耕地(墾田・池溝)のほかに、(三)山林、(四)採鉄地、(五)鉱山、(六)塩浜、(七)塩山、(八)港湾、(九)軍事基地、(一〇)漁場、(一一)牧場、(一二)猟場など一定の地域を占有するものに拡大され」たとの事である。
(2023/08/10)